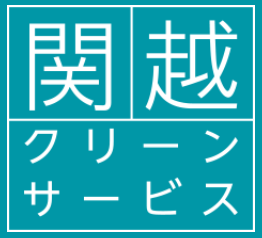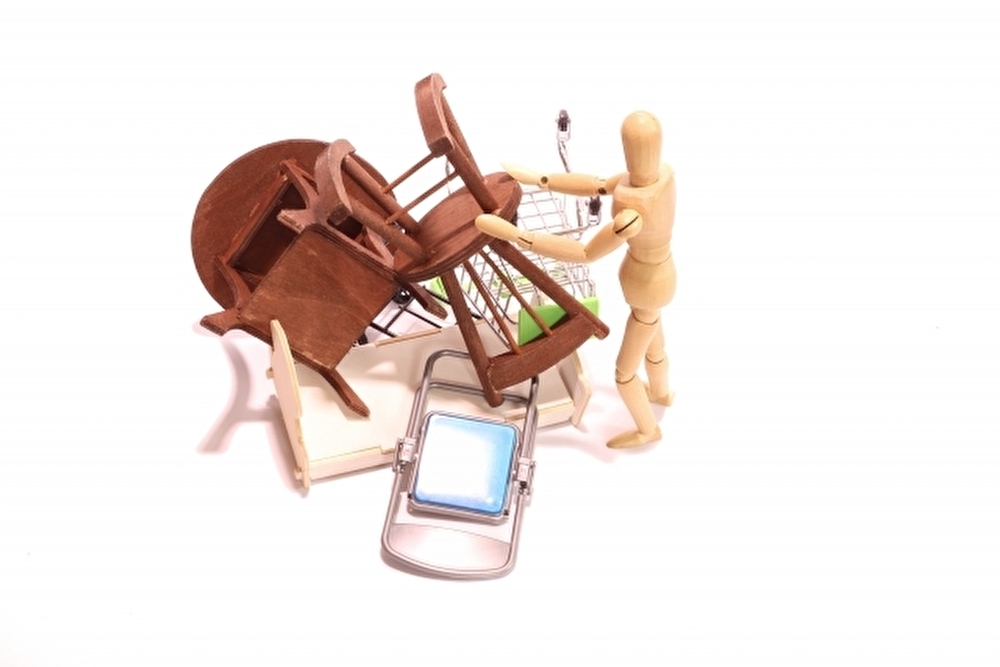家庭の玄関やオフィスの床につく黒い汚れ。これはヒールマークと呼ばれるもので、靴底のゴムなどが床に付着した跡です。この記事では、ヒールマークの落とし方について解説します。ヒールマークの予防策や原因もあわせて紹介するので、キレイな床をキープしたい方はぜひチェックしてください!
【床の黒い汚れ】ヒールマークとは?

最初に、ヒールマークの特徴をお伝えします。さらにヒールマークがつきやすい床も解説します。
ヒールマークの特徴
ヒールマークとは、床についた黒い線状の汚れのこと。靴や台車が通ったときの摩擦熱で靴底のゴムなどが溶け、床に付着することで発生します。特に以下のような靴はヒールマークがつきやすい傾向にあります。
- 革靴
- ハイヒール
- ブーツ
- ソールがゴム製・黒色
硬い素材や靴底の色が濃い靴はヒールマークがつきやすいです。人や荷物の出入りが多い場所ほどヒールマークがつきやすいため、こまめな掃除や予防対策が必要です。
ヒールマークがつきやすい床
ヒールマークは、以下のような床に付着しやすい傾向にあります。
- ホモジニアス系の床
- 塩化ビニル系の床
- ワックスが十分に密着していない床
床の素材が柔らかいと、靴底との摩擦で表面が傷つきやすく、そこにヒールマークが付着しやすくなるという悪循環にもなりかねません。また、塗布してから時間が経ったワックスは表面が柔らかく劣化しているため、汚れが付着しやすくなります。
石タイルやコンクリートなどの硬い素材の床はヒールマークがつきにくい特徴がありますが、床の素材を変えることは簡単ではありません。どのような素材の床でもキレイにキープするためには、こまめな掃除や予防が大切です。
床のヒールマークを放置するリスク
床のヒールマークを放置すると、以下のような3つのリスクにつながります。このようなリスクを回避するために、ヒールマークは早急に対応しましょう。
見た目が悪くなる
ヒールマークは黒い線や足跡のような見た目です。たくさんのヒールマークがついた床は見た目が悪くなります。ヒールマークがつくのは玄関やエントランスなど多くの人たちが行き来する場所に付着しやすいため、家やオフィス自体の印象が悪くなってしまうでしょう。
床の劣化が早まる
ヒールマークは見た目が汚れるだけでなく、床の素材を傷めてしまいます。ヒールマークの付着と除去を繰り返すことで床の表面が徐々に傷つき、美観を損なってしまうと、交換の費用や手間にもつながりかねません。床を長持ちさせるためにも、ヒールマークの対策は必要不可欠と言えるでしょう。
付着した汚れが、さらに汚れを吸着する
付着したヒールマークの表面はザラザラしています。その状態で放置していると、汚れの付着部分にさらにホコリなどが溜まりやすくなります。汚れがひどくなるほどこびりつきやすくなって掃除の手間がかかり、メンテナンスが大変です。メンテナンスを手軽にするためにも、定期的なヒールマークの掃除を心がけましょう。
床のヒールマークの予防方法

床にヒールマークがつくと掃除の手間がかかるうえに、汚れが落ちない場合もあります。ここでは床のヒールマークの予防方法について4つ解説します。
定期的にワックスをかける
フローリングワックスは床をコーティングし、傷をつけにくくする効果があります。ワックスは床材の表面に保護膜を作るため、ヒールマークが床に直接付着するのを防ぐ効果があります。ただし、ワックス自体に黒い汚れが付着するため、汚れが目立つ場合はワックス剝離剤を使って掃除しましょう。そして、新しくワックスを塗って、定期的に床を守る習慣をキープしてください。
スリッパを活用する
玄関やエントランスに入る前に靴をスリッパに履き替えることは、ヒールマークの予防方法のひとつです。オフィスであれば来客用のスリッパを用意し、スタッフには自分の履き替え用の靴を持参してもらうと効果的でしょう。
土足禁止にする
スリッパや代替の靴の用意が難しい場合、土足禁止にするという手段があります。わかりやすく貼り紙をしたり、下駄箱を設置したりするなど、土足禁止を徹底させるための環境が大切です。
マットを敷く
土足禁止にするのが難しい場所には、マットを敷くと無理なくヒールマークを防げるでしょう。床全体をカーペット素材にすることが難しい場合、ヒールマークがつきやすい場所にだけ玄関マットを敷くこともおすすめです。カーペットやマットはホコリや汚れが溜まるので、定期的な掃除・洗濯を心がけましょう。
ヒールマークの落とし方
ヒールマークがついたら、以下の3つのステップで掃除しましょう。ここで紹介するステップは自力で対応できる範囲のものなので、無理なく行うことが大切です。
1.モップや雑巾で拭き掃除する
まず、モップや雑巾で拭き掃除をします。ついたばかりのヒールマークであれば、洗剤を使わず水だけでも十分落とせるでしょう。水を使った拭き掃除は手間がかからないだけでなく床への負担も軽いというメリットがあります。ヒールマークはできる限り定期的に掃除し、メンテナンスの負荷を軽減させましょう。
2.メラミンスポンジでこする
拭き掃除で落ちないヒールマークには、メラミンスポンジが有効です。水を含ませて固く絞ったメラミンスポンジで、ヒールマーク部分を優しくこすってみましょう。
※注意点
メラミンスポンジは研磨作用があるため、強くこすると床のワックスやコーティングまで剥がしてしまう恐れがあります。必ず目立たない場所で試してから、軽い力で作業してください。
3.中性洗剤を使って掃除する
水拭きやメラミンスポンジでも落ちない頑固なヒールマークには、中性洗剤を使いましょう。中性洗剤をつけたスポンジや布でヒールマークを磨きます。床の素材によっては中性洗剤によって変形・変色などのリスクもあるため、必ず目立たないところでテストしてから掃除しましょう。
床のヒールマーク掃除の注意点

最後に、床のヒールマーク掃除の注意点について4つ解説します。床を美しく守るために事前にチェックしましょう。
床を強くこすりすぎない
ヒールマークを落とそうと床を強い力でこすると、かえって傷つけてしまうリスクもあります。硬い素材は避け、柔らかい布やスポンジ、ブラシを使いましょう。
床の素材に合った洗剤を選ぶ
床の素材と洗剤成分の組み合わせによっては床を傷つけてしまうため、素材に合った洗剤を選ぶことが大切です。床の素材と向いている洗剤は以下のとおりです。
- 塩化ビニル系:中性洗剤
- ラバー系床材:原則水のみを使用
塩化ビニル系の床は耐久性が強いという特徴があります。しかし、ワックス剥離剤のような洗浄成分が強力な洗剤は床を傷める可能性があるので、中性洗剤の使用がおすすめです。
ラバー系の床はデリケートなので、原則洗剤を使わず、水のみで掃除しましょう。ヒールマークが頑固でなかなか落ちないときは少量の中性洗剤で磨くという手段もありますが、必ず目立たないところでテストして、変色しないことを確かめてください。
しっかり床を乾燥させる
掃除した直後は水や洗剤の水分が残っているので、しっかり乾燥させましょう。水分が残っている床を歩くと、ヒールマークの原因になってしまいます。また、洗剤の成分が残るとベタつきの一因になるため、しっかり水でふき取ったあとに乾燥させることが大切です。
対応できないときは業者を検討する
「ヒールマークが頑固で落ちない」「掃除する箇所が広すぎて手に負えない」という場合、業者への依頼を検討しましょう。ヒールマークは放置するほどメンテナンスの手間がかかり、ますます対応が難しくなります。また、無理な掃除によって床を傷つけると、かえって汚れが増えたり床の寿命を縮めたりするなどのリスクにもなりかねません。床掃除のプロに依頼すれば専門的な技術や道具を使って、床の品質をキープしながらキレイに掃除できます。掃除と合わせてワックス塗装も一任すれば、ヒールマークの予防にもつながります。
まとめ|ヒールマークをなくして好印象な床を守る
この記事では、ヒールマークの落とし方について解説しました。
ヒールマークは、靴底のゴムなどが摩擦熱によって床に付着した黒い汚れです。玄関やオフィスのエントランスなど出入りが多い場所にできやすいという特徴があります。
ヒールマークは建物の見た目が悪くなるだけでなく、床の素材を傷めたり、掃除の負担が重くなったりするなどのデメリットにもなりかねません。スリッパやマットを活用して、ヒールマークの予防を心がけましょう。
自力で対応できないときは、掃除をプロに依頼するのもおすすめです。ヒールマークをなくし、美しい床を守りましょう。
関越クリーンサービスでは、オフィス清掃を行っております。以下のボタンよりお問い合わせください!