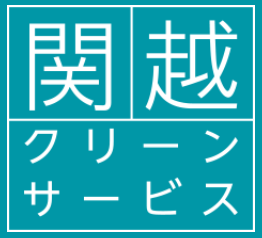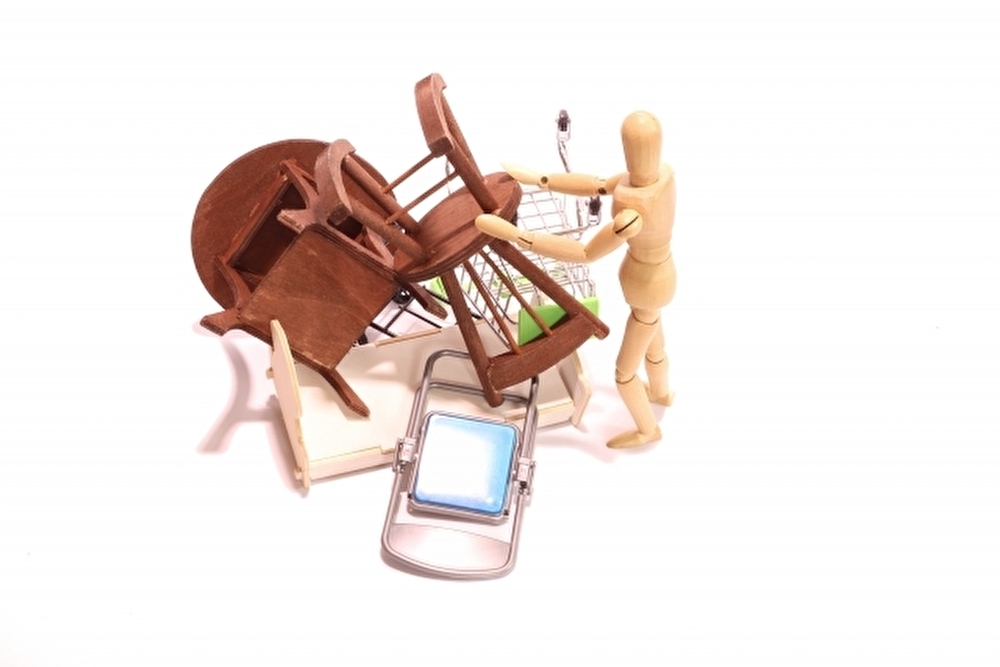オフィスや自宅のカーペット掃除にお困りの方、必見!カーペットは掃除を怠ると、衛生面や見た目を損なう上に、生地が傷み、寿命が縮んでしまいます。この記事では、シミ・液体など種類別のカーペットの掃除方法や日常のお手入れ方法について解説します。最後には業者に依頼するメリットもお伝えするので、ぜひチェックしてください。
カーペット掃除の注意点

最初に、カーペットを掃除するうえでの注意点について4つ解説します。間違った掃除方法でカーペットを傷つけてしまわないように、事前に確認してください。
素材に応じた掃除方法を選ぶ
カーペットは製品によって素材が異なり、適切な掃除方法も異なります。誤った方法で掃除すると、汚れが落ちなかったり、生地を傷めてしまったりするリスクもあるので注意してください。主な素材と掃除方法は以下のとおりです。
- 麻:原則掃除機をかければOK。水洗い不可。
- ウール:原則掃除機をかければOK。汚れたときは水拭きか衣料用中性洗剤での拭き掃除。
- ナイロン:原則掃除機で、水を使った掃除も可能。
- ポリエステル:原則掃除機で、水を使った掃除も可能。
- アクリル:原則掃除機をかければOK。汚れたときは水拭きか衣料用中性洗剤での拭き掃除。
とくに洗剤を利用する場合、カーペットの質が悪くなる可能性もあるので、必ず使用可能か調べてから掃除にかかりましょう。
汚れ具合や生活スタイルで掃除頻度を変える
カーペットの掃除は、汚れ具合や生活スタイルで頻度を変えるのがおすすめです。子どもやペットがいるご家庭、訪問者が多い場合は、カーペットが汚れる可能性も比較的高くなります。
カーペットの汚れは、すぐに対応できるかどうかがポイントです。面倒でも掃除回数を増やすのが効果的です。
アルカリ性洗剤や漂白剤を使わない
カーペットの掃除には、アルカリ性洗剤や漂白剤を使わないようにしましょう。洗剤の成分によってカーペットが変色・劣化するリスクがあるためです。漂白剤によって白くできても、一部分だけが不自然に白くなって、かえって違和感が出てしまう可能性もゼロではありません。
原則としてカーペットの掃除は掃除機と水だけで行い、どうしても汚れが落ちないときは、中性洗剤を使用してください。
生地を傷めるブラシや熱湯を使わない
汚れを落とすために、硬めのブラシでゴシゴシこすることはおすすめしません。カーペットの生地を傷めてしまい、毛が抜ける可能性があります。ブラシを使う場合、できるかぎり柔らかいものを使用しましょう。
汚れを浮かせるために熱湯を使うのも避けたほうが無難です。汚れの成分によっては、お湯をかけることで余計に落ちにくくなってしまいます。また、熱湯がカーペットの繊維を傷つけるリスクもあります。水またはぬるま湯で対応しましょう。
日常でできるカーペット掃除
次に、日常でできるカーペット掃除の方法について解説します。以下の4つは、手軽に日常に取り入れやすい方法です。
粘着ローラーを使う
粘着ローラーを使えば、手間をかけずに気軽に掃除できます。カーペットの縦方向にローラーを動かしたあと、横方向にも動かせば効果的です。粘着力をキープするため、一定以上汚れがテープに付着したら、適宜テープを交換しましょう。
ただし、毛足が長い・素材がデリケートなカーペットはローラーが届かなかったり、生地を傷めてしまったりするリスクもあるので、目立たない箇所でテストしてから掃除しましょう。
ブラシをかける
掃除機のヘッドブラシやヘアブラシ、洋服ブラシなどでカーペットのゴミをかき出せます。カーペットの毛並みと逆方向にブラシをかけ、出てきたホコリやゴミを都度取り除きましょう。
ブラシを使った掃除はデリケートな素材のカーペットに向いていますが、手間がかかるというデメリットがあります。大きなカーペットは掃除機のほうが手軽です。
掃除機をかける
ブラシで取り除けないゴミは、掃除機が有効です。カーペットの縦方向・横方向どちらからも掃除機をかけて、全体的にきれいにすることを意識しましょう。奥に潜り込んでいるゴミも吸い取るために、掃除機をゆっくりと動かすことがポイントです。回転ブラシつきの掃除機を使えば、ブラシと掃除機の手間を一括できます。
水拭きする・水洗いする
細かい汚れやニオイ対策として、月に1回程度水拭き・水洗いをすると効果的です。事前にカーペットの素材を確認し、水を使えるかチェックしましょう。
固く絞ったタオルやぞうきんでカーペットの表面を水拭きし、そのあと乾拭きしてください。そして、可能であれば陰干しをして完全に水気をなくしましょう。水気が残っていると、カーペットがカビ臭くなり、不衛生になります。外で干せない場合、サーキュレーターや扇風機を使って、カーペットを乾燥させましょう。
【状況別】カーペット掃除のポイント

ここでは、状況別のカーペット掃除のポイントについて解説します。カーペットの汚れによって、適切な掃除方法を選びましょう。
食べかすや毛がついているとき
食べかすや毛は、基本的に念入りに掃除機をかけて掃除すれば大丈夫です。ゴミの量が多い場合は、掃除機に加えて粘着ローラーをかけると効果的です。毛の長いカーペットは奥底にゴミが溜まって表面の掃除では不十分かもしれません。その場合、カーペットをひっくり返して、裏側からも掃除機をかけましょう。
液体をこぼしたとき
液体をこぼしたときは、その液体が油性か水性かで対処が異なります。どちらの場合も、タオル・ゴム手袋を用意し、窓を開けて換気できる状態で掃除にかかりましょう。タオルは色移りを防ぐために、白いものを使ってください。
・油性の場合油性の液体として、食用油やバターなどが挙げられます。タオルにベンジンを少量つけて、こぼした箇所をトントンと叩くように汚れを移し取ります。この動作を汚れが落ちるまで何度か繰り返しましょう。
または、市販のカーペット用油性シミ取り剤を使用し、製品の指示に従って汚れを落とすのもおすすめです。
カーペットの色落ちを防ぐために、事前に目立たない箇所でテストしてから、本格的な掃除に移ってください。
コーヒーやジュースなどの水性の液体をこぼした場合、カーペットの汚れた部分に少しだけ水を垂らして、すぐに乾いたタオルで叩いて吸い取ります。汚れが落ちるまで複数回繰り返しましょう。
水性の場合は水だけで対処できる場合もありますが、汚れてから時間が経った場合は落ちにくくなる可能性もあります。また、水をかけずぎると、かえって汚れを広げてしまうリスクもあるので注意してください。
シミがついているとき
液体や食べ物をこぼして時間が経ってしまうと、水だけではシミが落ちない場合があります。シミが手ごわいときは、布製品用の洗剤を使って掃除しましょう。濡れたタオルに洗剤をつけ、しっかりとなじませます。そのタオルで汚れを叩き、複数回繰り返して浮かせていきます。汚れが目立たなくなったら、最後は乾いたタオルで水気をふき取りましょう。
カーペット掃除を怠るリスク
カーペット掃除はついつい面倒で後回しになってしまうケースもあるでしょう。しかし、カーペット掃除を怠ると、以下のような4つのリスクにもなりかねません。これらのリスクを予防するためにも、カーペットは清潔に保ちましょう。
アレルギーを引き起こす
汚れたカーペットを使い続けると、ホコリやカビなどによってアレルギーを引き起こすリスクがあります。アレルギーを引き起こす要因として以下のものがあります。
- ホコリ
- 皮脂
- 髪の毛
- ペットの毛
- ダニ
皮脂や髪の毛は、日常生活を送っていると、どうしても知らない間にカーペットに落ちてしまいます。意識して掃除しなければ、あっという間に奥底に溜まるので注意しましょう。
食べカスや皮脂汚れは、ダニの好物です。とくに夏や梅雨どきはダニが増えやすい傾向にあります。くしゃみ・せき・皮膚炎など、あらゆるアレルギー症にも発展しかねないので、カーペットは清潔に保ちましょう。
見た目が汚くなる
カーペットの汚れを放置していると、見た目が悪くなります。さらに部屋全体の印象もイマイチになってしまいます。放置期間が長くなるほど汚れが落ちにくくなり、掃除のモチベーションも低くなってしまうでしょう。お気に入りのカーペットを美しくキープするためには、定期的な掃除が必要不可欠です。
悪臭につながる
汚いカーペットにはカビやホコリ、古くなった食べカス・飲み物のシミなどが多量に含まれています。複数の種類のニオイが混ざったまま放置していると、悪臭を発します。不快なニオイで生活に支障をきたさないためにも、悪臭の元となる原因を取り除きましょう。
カーペットの質が悪くなる
カーペットを掃除せずに放置すると、質が悪くなります。
見た目が悪くなるだけでなく、ホコリやカビなどによって、肌触りが悪くなってしまいます。繊維がごわついたり、毛足が立たなくなったりして、快適に使えなくなります。購入当初のフカフカ感やにおい、美しい見た目を守るために、こまめな掃除が欠かせません。
カーペット掃除をプロに任せるメリット

最後に、カーペット掃除をプロに任せるメリットについて3つ紹介します。カーペット掃除は、家庭や会社のスタッフで対応できる範囲に限界があります。必要に応じて業者に依頼して、清潔なカーペットをキープしましょう。
家庭では難しいカーペットの汚れを落とせる
家庭でのカーペット掃除に使えるアイテムは、水・ブラシ・掃除機・中性洗剤など限られています。そのため、頑固な汚れはなかなか落とせません。家庭の掃除では諦めてしまった汚れも、プロの専門的な技術や道具を使えばキレイにできる可能性があります。「お気に入りのカーペットを再びキレイにしたい」という人は、ぜひプロの力を借りてみてください。
カーペットの寿命を延ばせる
カーペットは適切な手入れによって寿命を延ばせます。とくにペルシャ絨毯のような高級でデリケートな素材は、家庭での誤った掃除によって傷めてしまうリスクもゼロではありません。カーペットを長く使いたい人は、プロの掃除を活用することをおすすめします。
コストを抑えられる可能性がある
カーペット掃除をプロに任せると、長期的に考えればコストカットになる可能性があります。カーペット掃除を業者に依頼する場合、1平方メートルあたり1,500円から6,000円程度のコストが相場です。高級なものであれば10,000円を超えるケースもあり、大きな出費と感じるかもしれません。しかし、プロの手入れによってカーペットの質を長持ちさせることによって、買い替えのコストを抑えられます。さらに企業の場合、掃除の手間や時間を節約でき、業務が効率化するというメリットもあります。
まとめ|カーペット清掃にはコツが重要
この記事では、シミ・液体など種類別のカーペットの掃除方法や日常のお手入れ方法について解説しました。カーペットは素材によって適切な掃除方法が異なり、誤った方法だとかえってカーペットを傷めたり、汚れがひどくなったりする可能性もあります。原則として家庭でのカーペット掃除には水・掃除機・ブラシを使い、頑固な汚れは中性洗剤を使いましょう。アルカリ性や漂白剤は、カーペットの劣化・変色になりかねないので、おすすめしません。
「カーペットを長くキレイに保ちたい」
「アレルギーのリスクを抑えてカーペットを使いたい」
このような人は、プロの掃除がおすすめです。専門的な技術や道具によって、家庭では落とせないカーペットの汚れが落とせる可能性があります。誤った掃除方法でカーペットを無駄にするリスクも回避できるでしょう。
関越クリーンサービスでは、オフィス清掃を行っております。以下のボタンよりお問い合わせください!